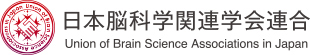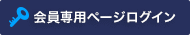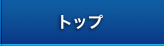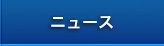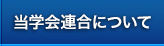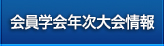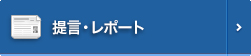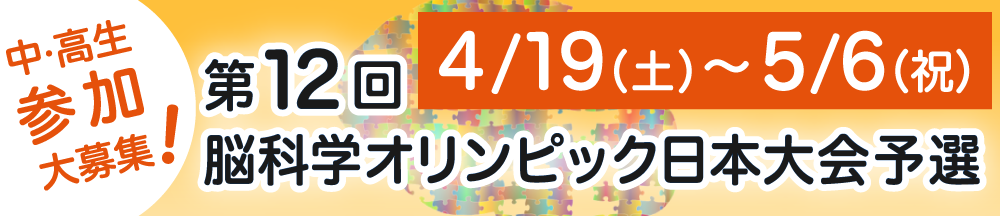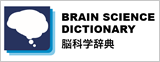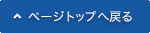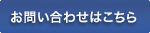第42回運営委員会
【日本脳科学関連学会連合 第42回運営委員会議事録】
日時
2025年2月16日(日)16:00~17:07
参加者
(敬称略)
高橋 良輔(代表 日本神経学会)
岡野 栄之(副代表 日本神経化学会)
池田 和隆(日本アルコール・アディクション医学会)
岩坪 威(日本認知症学会) 18:30 退出
上田 陽一(運営委員・日本神経内分泌学会)
柚﨑 通介(日本神経科学学会)
伊佐 正(代表補佐 日本神経科学学会)
鈴木 匡子(代表補佐 日本神経心理学会)
松田 哲也(代表補佐 日本ヒト脳マッピング学会)
山脇 成人(代補補佐・日本神経精神薬理学会)
武見充晃(産学連携諮問委員会WG4デジタル・ブレインタスクフォース長)
オブザーバー参加者
松井秀彰(庶務幹事)
古屋敷智之(会計幹事)
欠席者
加藤 忠史(副代表 日本生物学的精神医学会)
大隅 典子(日本神経精神薬理学会)
鈴木 匡子(代表補佐 日本神経心理学会)
議題:
(1)ニューロテクノロジー推進議員連盟(仮称)アカデミアリエゾンユニット設立について
議事内容
会議冒頭、高橋代表より経緯説明が行われた後、武見委員(産学連携諮問委員会WG4デジタル・ブレインタスクフォース長)より、ブレインテックがAI・医療・産業などに革新をもたらす技術であり、国際ルール策定への積極的関与が求められていることが説明された。日本では行政機関との連携が不足しており、国際機関からの情報を受けて議論・提案ができない状況があるため、「ニューロテクノロジー推進議員連盟(仮称)」の設立を提案し、アカデミア側事務局(リエゾンユニット)を脳科連の産学連携諮問委員会内に設置したい旨の依頼があった。
池田運営委員(産学連携諮問委員会委員長)から、脳科学の発展には法的枠組みへの関与が不可欠であり、議員との連携が重要であると指摘があった。
岡野副代表から、議連設立により省庁人事異動の影響を受けにくくなる点が評価された。
高橋代表からのリエゾンユニットの具体的な構想に対し質問があり、武見委員から、WG4メンバーが実働部隊となり、勉強会開催や議員との連携窓口を担うと説明があった。
議連の産業面での意義について、伊佐代表補佐から企業やベンチャーの関与が重要と指摘があり、武見委員から、アップルウォッチの例を挙げ、ルール整備が産業の発展につながると回答。国際ルール策定の実効性についても議論され、アメリカがいくつかの国際機関脱退後の不確実性はあるものの、継続的な取り組みの重要性が説明された。
柚崎運営委員から、リエゾンユニットの設置は重要だが、脳科連全体としての支援と可視化も必要との意見がだされた。また、議連趣旨書の「認知戦」に関する記載について、倫理的チェックの必要性が指摘された。
高橋代表から今後のタイムラインについて質問があり、武見委員からタイムラインについては、ゴールデンウィークを期限とし、参議院選挙前の設立が望ましいとの説明があった。
「認知戦」の安全保障上の意義に関する議論では、武見委員から、国民の危機意識を高めるための記載であり、議員の理解を促すものだと説明。松田代表補佐は、規制と研究推進のバランスについて質問され、武見委員より国内での議論が研究者を守ることにつながると回答された。議連の活用方法については、省庁・アカデミア間の意見共有や議論の場として機能することが確認された。松田代表補佐は、議連単体では機能しないため、具体的な政策提言のビジョンを持つことが重要であるとの説明があった。
岩坪運営委員も、官庁との連携が不可欠であるとの意見がだされた。
会議終了後、伊佐代表補佐より、趣旨書の記載について、国際競争の背景を明確にするための調整が必要と提案。脳科連として議連の設立をどのように扱うかについても議論が行われ、今後は提案ごとに検討していく方針が示された。また、脳科連に協力する関係者への丁寧に説明していくことが確認された。
最終的に、「ニューロテクノロジー推進議員連盟(仮称)アカデミアリエゾンユニット」の設立が全会一致で承認され、産学連携諮問委員会ではなく脳科連の運営委員会として設置することが決定した。
以上