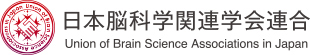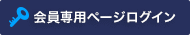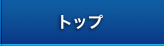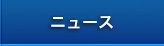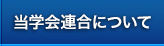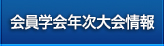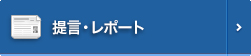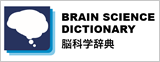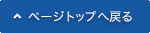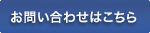第41回運営委員会
【日本脳科学関連学会連合 第41回運営委員会議事録】
日時
2025年1月8日(水)18:00~19:20
参加者
(敬称略)
高橋 良輔(代表 日本神経学会)
岡野 栄之(副代表 日本神経化学会)
加藤 忠史(副代表 日本生物学的精神医学会) 19:00 退出
池田 和隆(日本アルコール・アディクション医学会)
岩坪 威(日本認知症学会) 18:30 退出
上田 陽一(運営委員・日本神経内分泌学会)
大隅 典子(日本神経精神薬理学会)
柚﨑 通介(日本神経科学学会)
伊佐 正(代表補佐 日本神経科学学会)
鈴木 匡子(代表補佐 日本神経心理学会)
松田 哲也(代表補佐 日本ヒト脳マッピング学会)
山脇 成人(代補補佐・日本神経精神薬理学会)
動連協理事長:高田昌彦
学術会議分科会:加藤総夫
オブザーバー参加:松井 秀彰(庶務幹事)
議題:
(1)次期動物愛護管理法改正に関わる要望書について
議事内容
高田昌彦動連協理事長から、資料に基づき「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護管理法)改正についての今までの概要について説明がなされた。前回2019年の改正で、これまで除外規定として取り扱われてきた第10条「動物取扱業に関する規定」に対して附則第8条、例外規定として取り扱われてきた第41条「科学目的での動物利用に関する規定」に対して附則第9条が設けられた経緯などが説明された。この附則が組み入れられた場合は、生命科学研究等に重大な支障を来すおそれがあることが説明され、今回の改正において動物愛護管理法の第10条及び第41条は改正せず、現行の各種規制の下で機関管理体制を更に発展、充実させることを要望する要望書を提出する準備を進めていることが説明された。この要望書に日本脳科学関連学会連合にも賛同していただき、要望書に賛意団体として記載したいとの依頼があった。
加藤総夫日本学術会議動物実験分科会委員長より、日本学術会議の立場から要望書について以下の通り説明があった。
・日本学術会議は,2004年に報告「動物実験に対する社会的理解を促進するために(提言)」を発出して我が国の動物実験2006年体制設立の契機をもたらした。また,2023年には,日本学術会議報告「動物実験実施に関する共通基本指針の策定を中心とした機関管理制度の充実について」を発出し,2006年体制が成立して17年(当時)が経過して,わが国における動物を用いた科学を進めて行くうえでの透明性と客観性を担保する制度として有効に機能しており,それに基づいたさらなる維持と推進が重要であることを表明している。学術会議は,司法・行政などに対して「要望」する動連協の立場とは異なり,2006年体制を基盤として,適正な動物実験管理施策をさらに推進して人類の健康と生命医科学の進歩に貢献していくことを政府に対して「提言」していく立場にあるため,この要望書に要望者として名前を連ねることは考えていない。しかし,科学におけるその重要性を社会に向けて説明し,より充実した推進を図るべく,最終的なゴールとしては同じ方向を見ながら活動をしているとの認識のもと,このような活動の方向性は支持したい。
伊佐代表補佐より、要望書内の文言に、外部検証が周知徹底されていないところもあり、今後は外部検証の充実・強化に関する具体的な方策を検討していく、とあるが、動連協としてはどのような意味合いを持って記載されたのかと質問があった。
高田動連協理事長より、外部検証については文科省所属の大学・研究所では90%以上の達成率であるが、小さな大学や動物実験を行っている研究室がわずかしかない大学、文科系の大学では周知徹底されていないので、全体を計算すると60数パーセントの達成率である。今後は、もう少し詳細な実態調査を実施する必要があり、環境省もこの調査をもってすぐに動物愛護管理法の改正に踏み切ることはないであろうと考えている。
池田運営委員より動物実験の必要性を訴えるということで学術的な必要性を訴えるのは我々の役割だが、最終的には患者さんや家族会の方も賛同していただけるのが良いのではないか、そこへの働きかけはあるのかとの質問があった。
高田動連協理事長より、今回は間に合っていないが、今後はそういったことを検討する必要がある。2019年の改正時も急に附則がついたので、最後まで油断することなく関係団体ともよく話し合っていきたいとの回答があった。
高田昌彦動連協理事長、加藤総夫日本学術会議動物実験分科会委員長が退出後、要望書へ賛同をするかどうかの審議が行われ、出席者全委員一致で賛同の承認が得られた。
池田運営委員より、脳科連が要望書に賛同し要望書に脳科連の傘下にある学会名及び会員数を掲載する場合について、会員学会の了解を取ることが提案され、各会員学会へはメールで、1.要望書に賛同するかどうか、2.賛同の場合学会名を要望書に賛同団体として記載して良いかどうかの2点を伺うことが承認された。
以上